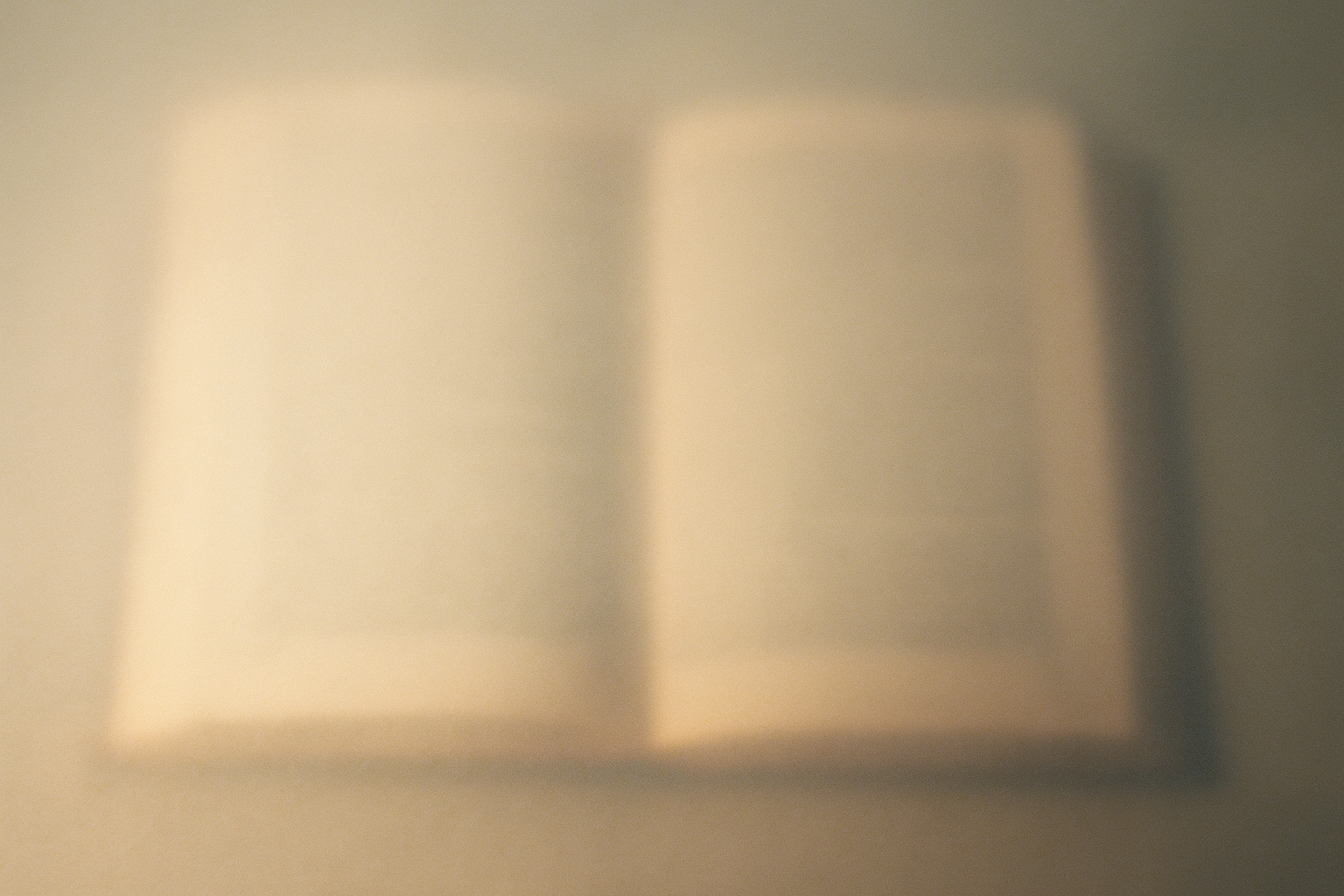最近ふと英語をすらすら読んだり話せるようになれたら仕事もプライベートも幅が広がりそうだなーと思って高校生ぶりに英語の勉強を始めているのですが、その中で結構こういう考え方にすると内容が入ってきやすくなるなと思った考え方があったのでまとめてみました。
ちなみに、まだ全然勉強途中なので、普通に英語喋れる人からしたら当たり前じゃん、と感じたり、そもそも的外れな内容もあるかもしれないのでその点はご理解ください🙇
英語を学んでいて感じた違和感
今回のテーマは多義語です。
英語を勉強していると、複数の意味を持つ単語によく出逢います。
たとえば have は「持つ」という意味が最もベーシックですが、「経験がある」と訳されることもあれば、have to で「〜しなければならない」と義務の意味になることもあります。
また like は「好き」と「〜のような」などの訳がありますし、leave に至っては「去る」と「残す」という、一見すると正反対に思える意味まで持っています。
学校教育や参考書では、こうした単語の用法を「多義語」として暗記するように説明されることが多いと思います。
でも、ふと色んな英文を読んでいる中でこれって実は一つの意味なんじゃない?と思うようになりました。実は、全部同じ意味の単語なんだけど、それを日本語に置き換えるときに複数の訳が生じているだけなんじゃないかなって。
haveは「持っている」で説明できる?
まずは have を例に考えてみます。
多義語として暗記しようとすると、「所有する」「経験がある」「〜しなければならない」などバラバラに見えます。
けれども、これらはすべて「持つ」という一点に集約できるように思います。
- I have a car.(私は車を持っている)
→ これはそのまま所有の「持つ」ですね。 - I have been to Paris.(パリに行ったことがある)
→ これは、パリに行った経験を「持っている」とも言い換えることができそう。 - I have to go.(行かなければならない)
→ 行くという「義務」を「持っている」と解釈できます。
日本語に直すと「経験を持っている」「義務を持っている」という言い方は少し不自然なので、それらが「経験がある」とか「しなければならない」と訳されているだけ。
そう考えると、have が多義語である必要はなくなります。
likeのコアイメージは「感覚的な距離の近さ」
次に like です。
日本人にとっては「好き」と「〜のような」の意味に訳されることがありますが、これも一つのイメージで説明できるのではないでしょうか。
私が感じるのは「感覚的な距離の近さ」というコアです。
- I like music.(私は音楽が好き)
→ 音楽との心理的な距離が近い。 - He looks like his father.(彼は父親に似ている)
→ 父親との外見的な距離が近い。
つまり、文脈によって「親しみ」というニュアンスになるか「類似」というニュアンスになるかが変わるだけで、根底のイメージは感覚的な「距離」が近いということ。
leaveは「離れる」から派生している
もう一つの例が leave です。
辞書を引くと「残す」と「去る」で、正反対のような訳が出てきます。
けれども、この単語のコアイメージを「基点から離れる」とすれば、どちらの意味にも説明がつきます。
- I leave my house.(私は家を出る)
→ 家から自分が離れるので「去る」と訳される。 - I leave my son.(私は息子を残していく)
→ 自分がその場を離れた結果、息子はそこに残る。だから「残す」と訳される。
日本語に直したときに「家を残す」では不自然だから「去る」と訳す。
でも、「息子を残す」は直訳でも自然だからそのまま「残す」と訳す。
言葉的には一見逆にも見えますが、実際は同じ一つのイメージから派生しているのだと思います。
学び方を変えるヒント
この視点で考えると、英語学習のアプローチも少し変わってきます。
「多義語を丸暗記しなければならない」という発想で考えると、覚えることも増えてくるし、訳す時もこれは〜〜構文だから、このhaveはきっと現在分詞で…みたいな感覚じゃなくてhaveが出てきたということはこの文章は(物理的か、概念的かはともかく)何かを所有しているという話なんだな。と感覚的に捉えやすくなります。
多義語というよりは「一つのイメージの派生」と捉えれば、例文を見ても迷いにくくなります。
まとめ
今回考えたように、ほとんどの場合、英語の多義語は本当は存在せず、ほとんどの単語は一つの意味に帰着できるのではないかと思います。
have、like、leave など一見すると複数の意味を持つ単語も、コアイメージで説明すればすっきり整理できる。
英語を勉強する中で、「これは別の意味なんだ」と切り分けるよりも、「根っこのイメージは同じなんだ」と考える方が、ずっと理解が深まりやすい気がしています。
英語得意な人からしたら当たり前のことかもしれないけど、個人的にちょっとした発見のように感じたのでまとめてみました。